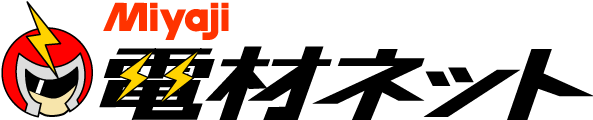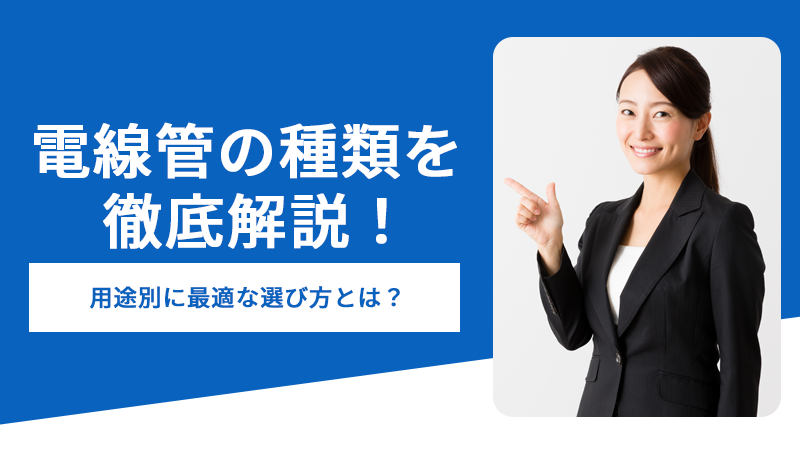電線やケーブルには複数種類があり、それぞれ特徴も異なります。使用する環境に合わせて電線やケーブルを使用する必要があるため、電線やケーブルの種類や特徴を理解しておくことが大切です。また、電線やケーブルは状況に応じて適切な太さに変える必要があります。今回は電線やケーブルの種類や特徴、太さや決め方について解説します。
目次
電線・ケーブルの種類
電力用電線
電力用電線は、発電所から住宅や商業施設などに安全かつ効率的に電気を送るために使用される電線のことで、以下のような種類があります。
- IV
- CV
- VVR
- DV
IVは600V以下の屋内配線に使用される電線で、耐水性や可とう性、難燃性などの特徴があります。許容温度は60度であり、直射日光があたる屋外では60度を超えることもあるため、基本的に室内で使用されます。
また、CVケーブルは使い勝手がよく、構内ケーブルとして使用されることが多く、主流のケーブルともいえるでしょう。心線を増やしたものはCV-2C~CV-4Cと呼ばれ、単体の場合よりも許容電流が大きくなるといった特徴があります。
通信ケーブル
音声や画像・映像を送るためのケーブルです。音声で受け取ったデータを電気や光の信号に変えることで、機器間で信号の接続ができるようにします。情報を光のように運んでいくイメージです。 通信ケーブルには以下のような種類があります。
- CPEV
- FCPEV
- AE
- UTP
CPEVは、特定の電力機器に使用される専用のもので、特定の電圧と電流の要件を満たすために設計されています。
FCPEVは光ファイバーケーブルのひとつで、一度に多くの情報を送ることができるうえ、データが送信されてから受信されるまでの時間が短いといった特徴があります。また、高電圧の場所や環境の影響を受けやすい場所、可燃性ガスなどの危険な場所でも安全に使用できるといった特徴もあります。
制御・防災ケーブル
制御ケーブルとは制御回路に使用するケーブルのことで、電線配線には絶縁電線を用います。また、防災ケーブルとは災害時に重要な情報を伝えるためのものです。地震や台風といった自然災害時でも、電話やインターネットによる通信を維持できるといった特徴があります。以下のようなケーブルが制御・防災ケーブルになります。
- CVV
- CEV
- FP
- HP
CVVは線心数が幅広く展開されているため、用途に合わせて使用できます。使用場所はエアコン、計測機器、自動制御配線などです。FPは、電線が高温や火災に対する高い耐火性能を持っているといった特徴があります。
消火栓や排煙機など、防災機器への電気を送るときに使用されます。
そのほかの特殊電線
ほかにもFA用・産業機械ケーブルなどの特殊電線があります。FA用は、Factory Automationの略で、工場自動化の意味を示しています。生産工程の効率化・自動化を目的とするロボットなどのFAシステム機器間の接続に使われます。
FA用には、可動用・固定用、制御ケーブルなどが使用されます。使用する機器によって必要な性能が異なるため、それに対応できるよう幅広い種類があります。電気機器や家電製品の内部配線に使用されるのが産業機械ケーブルです。
主な種類に、平型コードやキャブタイヤ、ビニル絶縁電線などがあります。キャブタイヤは電気を通しながら移動が可能なケーブルで、耐熱性や耐水性が高いといった特徴があります。使用場所は、トンネル工事で使用される機器や工場内のクレーン、エレベーターなどです。
電線とケーブルの違い
ここからは電線とケーブルの違いについて解説します。
電線の特徴
電気を通す目的で使用されるものは全体的に「電線」として扱われており、電線は電気を通す導体のまわりを絶縁体で覆われています。よく目にするものといえば、各地域にある電柱にかかっている電線などがあります。
各電線は、種類によって耐水性や可とう性などの特徴が異なります。また、電線を覆っている絶縁材が安全に使用できる許容温度も異なるのです。電線は屋内・屋外、常に高温状態である危険な場所など、さまざまな場所に設置する必要があるため、各電線の特徴や許容温度に適した電線を選び設置することが重要といえます。
ケーブルの特徴
ケーブルとは絶縁材料で覆った複数の電線の外側を保護するシースで覆い、ひとつにしたものです。シース→絶縁体→導体の順で保護されています。シースの目的は電線やケーブルを保護したり、絶縁したりするためです。
シースで覆われていない電線よりも優れている点は以下となります。
- 保護:外部からの接触や摩耗から守る
- 耐候性:太陽光による紫外線から守り、ケーブルや配線の効果を長く維持する
- 絶縁:ほかのケーブルや外部との接触による感電やショートが起こるリスクを減らす
また、電線よりも種類が多く、電力や制御・計装用・通信ケーブルなどさまざまな種類に分けられています。それぞれが異なる目的や用途に合わせて設計されており、使用環境や電圧・電流、信号の種類などによって適したものを選び、設置することが重要です。
電線とケーブルの違いを比較
電線とケーブルの違いは、電線のまわりを覆っているシースがあるかないかの違いです。まず、電線については「電気設備に関する技術基準を定める省令」で以下のように定められています。
「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
一方、ケーブルについては光ファイバーについてのみ記載されており、全体的なことについては定義されていません。そのため、電線の一部という認識で扱われている場合が多いです。
また、特徴や使用場所にも違いがあります。ケーブルは多くの環境条件に耐える設計がされているため、さまざまな産業用途で使用されています。それに対して、電線は屋内で使用されることが多く、柔軟性が高いですが耐候性や保護性が低いといった特徴があります。そのため、それぞれの用途に応じて電線とケーブルを使い分けることが重要といえるのです。
電線の太さの決め方
ここからは電線の太さがどうやって決まるのかについて解説します。
屋内配線
屋内配線として使用される絶縁電線は、電線を被っている絶縁材料により、耐熱温度が異なります。たとえば、架橋ポリエチレン絶縁電線の耐熱温度は90度で、耐熱温度が60度の塩化ビニル絶縁電線よりも高いです。そのため、耐熱温度が高い電線は電線使用時に生じる熱を処理でき、電線を損傷するおそれがないため、電線を細くできます。しかし、塩化ビニル絶縁電線は耐熱温度が低く、損傷するおそれがあることから以下のような太さが必要です。
- 金属管、金属ダクト、プラスチック管などに電線を引き込む:3条以下では22m㎡
- 許容電流を得るために7~15条を引き込む場合には38m㎡
また、配線が長いと電線の抵抗が起き、電圧が減少するため、機器が正常に作動しない可能性が出てきます。よって電圧降下を防ぐために、抵抗の小さい太い電線を選ぶこともあります。
架空配電線
架空配電線の太さは、安全性を確保するため、耐張強度を基準に決定されます。電圧に応じて異なる基準があり、300V以下の低圧線は、引張り強さ3.44kN以上または直径3.2mm以上の硬銅線が求められます。
300Vを超える低圧・高圧線については、市街地では引張り強さ8.01kN以上または直径5mm以上、市街地外では5.26kN以上または4mm以上の硬銅線が必要となります。架空配電線は空中に設置されているため、各電線が十分に離れており、良好な空気循環と放熱が可能です。これにより電線同士の熱干渉を最小限に抑えることができるため、電線の材質と太さが最終的な許容電流を決定する重要な要因となります。
地中電線路
地中埋設電線ケーブルの導体サイズは、複数の要因により大きく変化します。定格電圧、ケーブルの種類、絶縁材料の特性が異なるため、同一の許容電流でも必要な導体サイズが変わります。
とくに土壌の熱的特性が重要で、土壌の熱抵抗が高いほど熱を逃がす能力が低下し、許容電流が小さくなります。 さらに、同一場所に敷設するケーブルの本数が多いと、各ケーブルから発生する熱が重なり合い、全体の温度上昇を引き起こすため、許容電流が減少する可能性があります。これらの要因により、適切な導体サイズの選定が必要です。
瞬時許容電流
電線の種類や設置方法に関係なく、電線の負荷側で短絡が発生すると、その短絡電流は電線全体を通過します。短絡が起こると通常の負荷電流よりもはるかに大きな電流が瞬時に流れ、電線が熱くなります。
短絡電流が流れる時間は1秒以下ですが、熱は電線内部に蓄積し、絶縁体の強度や引張り強度の低下だけでなく、電線全体を使えなくする作用があるのです。瞬時許容電流とは電線が一瞬の短絡電流に耐えられる最大電流量のことで、電線の材質や太さによって決まります。
たとえば通常の使用で22mm²の電線が十分な場合でも、瞬時許容電流のために100mm²が必要になることがあるのです。設置済みのケーブルで短絡容量が増え、瞬時許容電流が不足し、電線の交換が難しい場合は、短絡保護継電器の設定の変更も検討する必要があります。
超高圧架空電線
超高圧架空電線では、電線の表面の電界(電気力線の密度)が非常に強くなります。空気の絶縁耐力(電気を通さない能力)を電線表面の電界が越えると、表面に放電現象が起こります。これをコロナ放電といいます。
コロナ放電は電波障害を引き起こし、エネルギー損失をもたらすため、電線を太くし、電線の表面の電界を弱める必要があります。 しかし、電圧に比例して電線の表面の電解も強くなり、より太い電線が必要になることから複導体を使用し、効率的に緩和する必要があるのです。
こちらの記事では、電線管の種類について解説しています。電線管を選ぶポイントや特徴・用途も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
電線管の種類を徹底解説!用途別に最適な選び方とは?
電線管は、電線を保護し、安全に配線するために欠かせない設備です。配線の環境や用途に応じて選べるさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解することが重要です。本記事では、電線管の基本知識から用途に合わせた選び方までを解説します。
まとめ
電線とケーブルには複数の種類や異なる特徴があるため、用途に適したものを選ぶことで安心・安全に電気を送れます。また、屋内配線や架空配電線、地中電線路など使用する場所や状況に応じて電線の太さを調節する必要もあります。
電線とケーブルを設置する際には、各電線やケーブルの種類を知り、見分け方を理解することが重要といえます。
電材ネットでは10万点以上の商品を取り揃えていますので、電気工事で電線やケーブルが必要な場合はすぐ取り寄せられて便利です。当日15時までの注文で当日発送も可能ですので、ぜひご利用ください。また電材ネットではユーザー登録していただくと、お気に入り登録や再注文機能が利用できるためおすすめです。