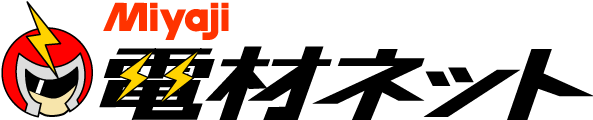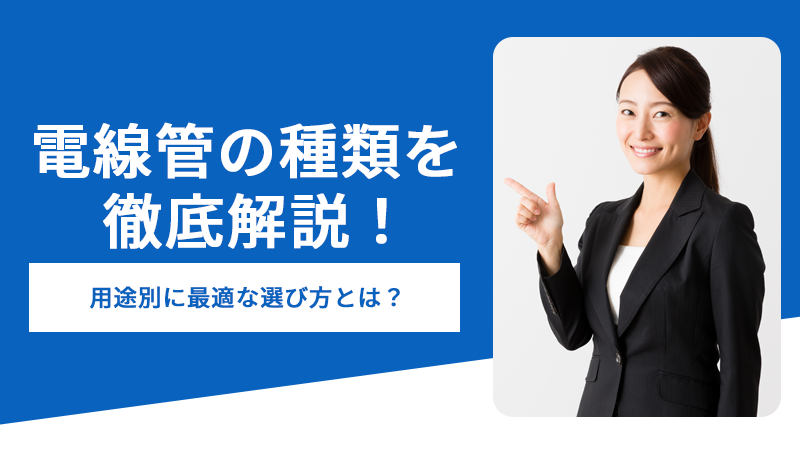
電線管は、電線やケーブルを保護するために用いられる管(パイプ)です。普段は目にする機会が少ないため、どのように生活に役立っているかを知る人は少ないでしょう。一口に電線管といっても、材質や形状、サイズは多岐にわたり、それぞれに特有の特徴や利点があります。 本記事では、電線管の基本的な役割や種類を解説します。また、使用環境や用途に応じた最適な選び方について詳しく紹介します。
目次
電線管とは

電線管は、電線を守るためのパイプ状の製品で、外部からの損傷や劣化を防ぐ役割があります。使用環境に応じたさまざまな種類が販売されており、適切なものを選んで利用できるでしょう。
電線管は、電線を物理的なダメージや環境要因から保護することで、漏電や火災といったトラブルを未然に防ぎます。また、屋内外問わず幅広い場所で使用され、屋外では街灯、高速道路、トンネル、電気メーター周辺の配線保護などに活用されています。 屋内では、工場の機械周りやLANケーブル、ビルや学校の電気配線などに使われることが一般的です。さらに、天井裏など目に見えない場所にも設置され、生活を安全に支える重要な役割を果たしています。
電線管の種類
電線管にはさまざまな種類があり、形状や用途によって使い分けられています。ここでは、それぞれの種類について詳しく解説します。
形状別
電線管の形状は「直管電線管」と「可とう電線管」の2つです。
直管電線管
直管電線管は、まっすぐな棒状の形状をした電線管です。このタイプの電線管は、曲げられないため、おもに直線的な経路での配線に適しています。
直管電線管の大きな特徴は「強度の高さ」です。外部からの衝撃に強く、耐久性にも優れており、過酷な環境下でも電線をしっかりと守ります。 また、直管電線管は露出配管として使われることが多く、ビルの屋上や学校の設備などでよく見かけます。耐久性と強度を活かして、地中埋設管として使用させている場合もあります。
可とう電線管
可とう電線管は柔軟性を持つ電線管で、直管電線管では対応できないような複雑な場所に最適です。この電線管は自由に曲げられるため、設置場所の制約が少なく、幅広い施工に対応できます。
とくに、建物内部の機械周りや狭いスペースなど、角度を変えながら配線する必要がある場所での作業に適しています。
また、可とう電線管のもうひとつの利点は、施工が比較的容易である点です。柔軟性があるため、作業者は現場で必要な長さや形状に合わせて簡単に加工でき、設置にかかる時間を短縮できます。 そのため、工場や機械設備、住宅の配線作業など、さまざまな用途で活用されています。
素材別
次に、電線管を素材別に分類し、それぞれの特徴と用途について解説します。ここでは、電線管を「金属製」「合成樹脂被覆鋼管」「合成樹脂」の3つの素材にわけて紹介します。
金属製
金属製の電線管は、強度と耐久性から非常に高い評価を受けており、おもに以下の4つの種類です。
C管は、金属の厚みが薄く、軽量で取り扱いやすい電線管です。おもに屋内や天井裏の露出配線に使用されています。ただし、耐候性が低いため、屋外での使用には向いていません。
G管は、溶融亜鉛メッキが施された肉厚な管で、高い耐候性と耐腐食性を持っています。そのため、直射日光が当たる場所や雨風にさらされる環境でも長期間メンテナンスが不要です。おもに屋外や過酷な環境下で使用され、工場の配線や屋外施設での露出配管に適しています。
E管は薄溝電線管よりもさらに薄い管で、ねじ切り加工が不要な「ねじなし電線管」として知られています。G管やC管と比較すると、内部に収容できる電線の本数が多く、効率的な配線が可能です。おもに屋内や天井裏で使用され、特に配線スペースが限られる場合に役立ちます。 金属製可とう電線管は、金属の堅牢さを持ちながらも柔軟性を兼ね備えています。複雑な曲げ加工が可能で、狭い空間や機械周りなどの施工に適しています。コストはほかの金属製電線管より高めですが、その多用途性から幅広い環境で利用可能です。
合成樹脂被覆鋼管
合成樹脂被覆鋼管は、鋼管に樹脂コーティングを施した電線管で、防食性や防水性に優れており、おもに2種類あります。
まず、ポリエチライニング電線管です。この電線管は、外面2層と内面1層のエポキシコーティングが施され、防腐性に優れています。屋外や地中埋設配管に適しており、耐久性が求められる環境で使用されます。地下配線や水気の多い場所でも安心して利用できるのが特徴です。 次に、フレキシブル電線管です。合成樹脂被覆鋼管製の可とう電線管で、ビニル皮膜が施されています。そのため、防水性や耐油性に優れており、屋内外を問わず多様な環境で使用できます。配線経路が複雑な場合に適しており、施工の柔軟性が高い点が魅力です。
合成樹脂
合成樹脂製電線管は、軽量でコストパフォーマンスに優れている点が特徴です。おもに以下の4種類が使用されています。
- VE管
- PF管
- CD管
- FEP管
VE管は、金属製電線管より軽量で取り扱いやすく、コスト面でも優れています。また、錆びないため絶縁性や美観性が高い点が特徴です。一方で、外的衝撃に弱いため、耐久性が求められる環境には向きません。
PF管は、合成樹脂製の可とう電線管で、自己消火性を持っています。隠蔽配管や露出配管に使用でき、屋内外問わず利用可能です。柔軟性が高く、配線作業が複雑な場合にも適しています。
CD管は、合成樹脂製の可とう電線管で、自己消火性を持たないため、コンクリート埋め込み専用として使用されます。地中配線や壁内部に埋設する配線作業で役立つでしょう。 FEP管は、衝撃や圧力に強い合成樹脂製電線管で、おもに地中埋設配管として使用されます。耐久性が高く、地下環境における長期間の使用に適しています。
電線管選びのポイント

電線管を選ぶ際には、設置環境や使用条件をしっかりと把握することが重要です。
適切な電線管を選ぶことで、配線の安全性や耐久性が向上し、トラブルを未然に防ぐことができます。しかし、電線管選びは単純に材質や形状を選ぶだけでは不十分であり、周囲の環境や施工条件を考慮する必要があります。
まず、天候や湿気の影響を考慮しましょう。屋外に設置する場合や湿度が高い環境では、耐候性や防水性、耐腐食性に優れた素材の電線管が求められます。一方、屋内であれば、軽量で取り扱いやすい合成樹脂製電線管や、配線の美観を保てるタイプが適しているでしょう。
また、建物の形状や施工現場の特性も重要なポイントです。たとえば、狭い空間や複雑な配線経路では、柔軟性のある可とう電線管が適しています。逆に、直線的な配線が多い場合は、耐久性が高い直管電線管が適するでしょう。
さらに、電線管を選定する際には、事前の現地調査が不可欠です。机上の計画だけで配管を決定すると、実際の施工時に問題が生じることがあります。
現地調査では、配線ルートの確認や周辺環境の特性を細かく把握し、それに基づいて必要な電線管やその他の資材を選ぶことが大切です。 最後に、入念な調査と適切な電線管の選定は、配管工事を長持ちさせるための基本です。これにより、故障やメンテナンスのリスクを最小限に抑えられます。正しい選択が、安全で効率的な配線工事の第一歩となるでしょう。
こちらの記事では、電線・ケーブルについて解説しています。太さの決め方や種類も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
電線・ケーブルの種類と特徴は?太さの決め方と合わせて解説
電線とケーブルには複数種類があり、特徴や環境などに適した種類を選ぶことが重要です。また、状況に応じて太さを変更する必要もあります。適切な設置を行うためには、各種類の特徴や太さの決め方を理解することが大切です。
まとめ
電線管は、電線を保護し、安全に配線するために欠かせない設備です。配線の環境や用途に応じて選べるさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解することが重要です。
設置環境や施工条件を考慮し、適した素材や形状の電線管を選ぶことで、トラブルを防ぎ、長期間にわたる耐久性を確保できます。また、事前の現地調査を入念に行い、実際の使用環境に合った製品を選定することが重要です。
電線管工事を計画する際、必要な資材を購入する場所として「電材ネット」をご利用ください。
「電材ネット」は電気工事店や現場をサポートするためのネットストアで、電線やケーブル、配管材など多種多様な商品を取り扱っています。品揃えは10万点以上と豊富で、安心して必要な商品を見つけられます。 配線工事の際にはぜひ「電材ネット」を活用して、安全で効率的な施工を実現してください。